ファミリー層向けカスタマージャーニー戦略:5つの見出し
# ファミリー層のカスタマージャーニーを理解する:効果的なマーケティング戦略の鍵
ファミリー層向けのマーケティングは、単なる製品やサービスの宣伝にとどまりません。家族という複雑な意思決定ユニットの行動パターンと心理を深く理解し、彼らの旅路(カスタマージャーニー)に寄り添うことが成功の鍵となります。日本の家族構造や価値観が変化する中、ファミリー層を対象としたマーケティング戦略も進化が求められています。
ファミリー層マーケティングの特殊性と重要性
ファミリー層は、日本の消費市場において最も購買力の高いセグメントの一つです。総務省の家計調査によれば、子どものいる世帯の消費支出は平均して子どものいない世帯より約25%高いというデータがあります。しかし、この市場へのアプローチには独自の複雑さが伴います。
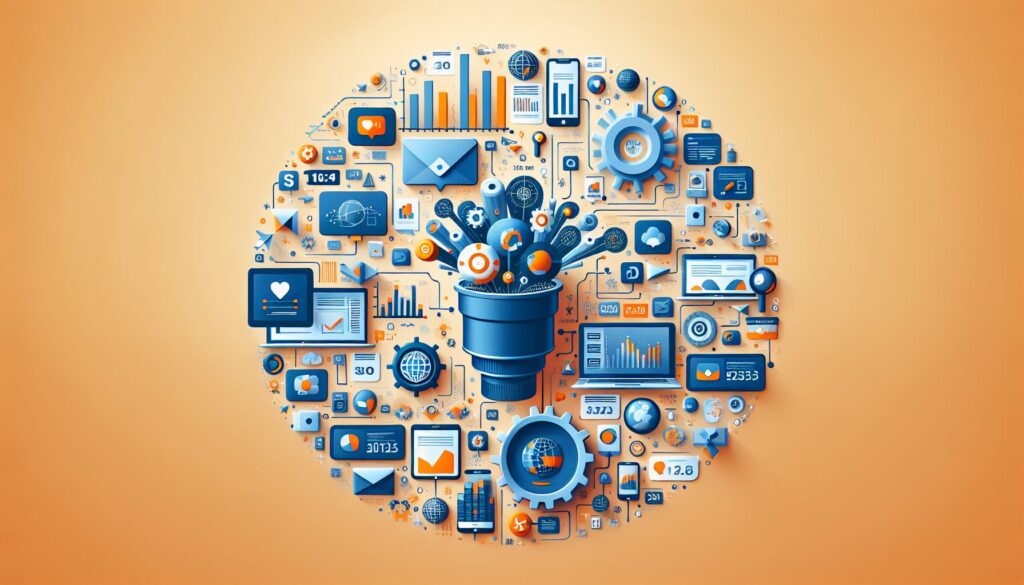
ファミリー層向けマーケティングの特徴は、「複数の意思決定者」が存在することです。親(父親・母親)、子ども、場合によっては祖父母までもが購買決定に影響を与えます。各メンバーが異なるニーズ、欲求、影響力を持っており、これらすべてを考慮したカスタマージャーニー設計が必要になります。
特に日本のファミリー層においては、安全性、信頼性、教育的価値といった要素が購買決定において重視される傾向があります。博報堂生活総合研究所の調査によれば、日本の親の78%が「子どものために良いと思うものには惜しみなくお金をかける」と回答しています。
ファミリー層のカスタマージャーニーの5つの段階
ファミリー層のカスタマージャーニーは、一般的なフレームワークを基盤としながらも、家族特有の要素を考慮する必要があります。以下に5つの主要段階とそれぞれのポイントを解説します:
1. 認知段階(Awareness):ファミリー層が問題や欲求を認識する段階
– 子育て中の親は時間的制約が大きいため、効率的な情報収集を好む
– 口コミや信頼できる情報源(育児雑誌、ママ友のSNS等)の影響力が非常に大きい
– 子どもの成長段階に応じた悩みや関心事が変化する
2. 検討段階(Consideration):解決策や選択肢を比較検討する段階
– 家族会議やパートナーとの相談が行われることが多い
– 子どもの意見が年齢に応じて重視される(特に6歳以上)
– 安全性、教育的価値、コストパフォーマンスなどの複合的な評価軸
3. 決定段階(Decision):最終的な購買決定を行う段階
– 最終決定者は商品カテゴリーによって異なる(例:食品は母親、電化製品は父親が決定権を持つ傾向)
– 試用体験や返品保証などのリスク低減策が重視される
– 時間的・金銭的コストの総合評価
4. 体験段階(Experience):製品・サービスを実際に使用する段階
– 家族全員の満足度が重要(一人でも不満があると再購入率が下がる)
– 子どもの反応が次回購入の大きな決定要因になる
– 期待と現実のギャップが大きいと不満足度が高まる
5. 絆形成段階(Bonding):ブランドとの関係性を構築する段階
– 家族の成長に合わせたアップセルの機会(子どもの成長に合わせた商品提案など)
– ロイヤルティプログラムへの参加意欲が高い(特に家計管理者)
– 家族の思い出と結びついた製品・サービスへの愛着が強い
日本のファミリー層の特徴と変化するニーズ
日本のファミリー層マーケティングを考える上で、近年の社会変化を理解することが不可欠です。核家族化の進行、共働き世帯の増加、父親の育児参加、デジタルネイティブな親世代の台頭などが、カスタマージャーニーに大きな影響を与えています。
電通の「ファミリーマーケティング白書2022」によれば、コロナ禍以降、家族で過ごす時間の価値が再評価され、「家族体験」を重視する消費行動が増加しています。また、Z世代の親たちは自分自身のライフスタイルを大切にしながら子育てをする「ニュー・ペアレンティング」の傾向が強まっており、従来の「子ども中心」のマーケティングだけでは響かなくなっています。

これらの変化を踏まえたカスタマージャーニー設計が、ファミリー層向けマーケティングの成功には不可欠なのです。次回のセクションでは、各段階における具体的な戦略とアプローチ方法について掘り下げていきます。
ファミリー層の特性と消費行動:最新データから見るマーケティングターゲットの変化
日本のファミリー層が持つ独自の消費特性
日本のファミリー層は、単なる「子どもがいる世帯」という定義を超えた複雑な消費主体です。最新の総務省統計によれば、日本の世帯構成は急速に変化しており、従来の「両親と子ども2人」という標準家族像は全体の18.5%にまで減少しています。一方で、共働き世帯は全世帯の68.1%に達し、消費決定プロセスにも大きな変化が生じています。
このようなファミリー層の変化は、マーケティングターゲットとしての捉え方にも革新を迫っています。特に注目すべきは以下の3つの特徴です:
- 共同意思決定の増加:購買決定が家族メンバー間の協議によって行われるケースが増加(特に高額商品で顕著)
- 時間価値の重視:共働き世帯の増加により「時間節約」「効率性」を重視する傾向が強まる
- 子ども主導の消費行動:子どもの意見が家族の消費選択に与える影響力が拡大(特にデジタル関連製品・サービス)
デジタル時代におけるファミリー層の消費行動変化
スマートフォンの普及とSNSの発達は、ファミリー層の情報収集と購買行動に革命的な変化をもたらしました。電通の最新調査によれば、日本のファミリー層の92%が購入前にオンラインでの情報収集を行い、そのうち78%がSNSでの口コミを重視しています。
特に顕著なのは、マルチデバイスでのカスタマージャーニーです。ファミリー層は平均して3.2種類のデジタルデバイスを使い分け、購買プロセスの各段階で異なるデバイスを活用する傾向があります。例えば、初期情報収集はスマートフォン、詳細比較はタブレットやPC、最終購入決定はまたスマートフォンに戻るという行動パターンが確認されています。
これはマーケティング戦略において、オムニチャネル対応の重要性を示しています。各チャネルでの体験が一貫しており、かつシームレスに連携していることが、ファミリー層の獲得と維持に不可欠なのです。
世代別・家族構成別の消費特性マトリクス
ファミリー層と一口に言っても、その内部構造は多様です。効果的なマーケティングターゲティングのためには、より細分化された理解が必要です。
| ファミリータイプ | 主な消費特性 | 効果的なアプローチ |
|---|---|---|
| 乳幼児を持つ新興ファミリー | 安全性重視、情報収集に熱心、初めての体験に対する不安 | 専門家の保証、詳細な情報提供、コミュニティ形成 |
| 小学生を持つ成長期ファミリー | 教育投資増加、子どもの意見尊重、家族共有体験重視 | 教育的価値の提示、子ども向けコンテンツ、家族体験の創出 |
| 思春期の子を持つ成熟ファミリー | 個別化する消費、親子間の価値観相違、高額商品への投資 | 世代間ギャップを埋める提案、個別化と共有のバランス |
注目すべきは、これらの各ファミリータイプがカスタマージャーニーの各段階で異なる行動パターンを示すことです。例えば、乳幼児を持つ家族は「認知」段階で専門家の意見や安全性証明を重視しますが、思春期の子を持つ家族は「検討」段階で子ども自身の意見や同世代のトレンドを重視する傾向があります。
マーケティングターゲットとしてのファミリー層の今後
少子高齢化が進む日本において、ファミリー層は量的には縮小していますが、質的にはその重要性を増しています。特に、一世帯あたりの消費支出は増加傾向にあり、子育て関連サービスへの投資意欲は高まっています。
日本政府の少子化対策の強化に伴い、今後はファミリー層を支援するサービスへの需要がさらに高まると予測されます。特に「時間の有効活用」「教育効果」「家族の絆強化」という3つの価値軸を満たすサービスが市場で成功する可能性が高いでしょう。
マーケティング担当者にとって重要なのは、変化するファミリー層のニーズを継続的に追跡し、カスタマージャーニーの各段階で適切なタッチポイントを設計することです。従来の「ファミリー向け」という大きなくくりではなく、より細分化されたペルソナ設計と、それに基づいたカスタマイズされたアプローチが成功への鍵となります。
家族の意思決定プロセスを理解する:ファミリー層特有のカスタマージャーニーマップの作り方
ファミリー層特有の意思決定プロセスとは
ファミリー層のカスタマージャーニーを理解する上で最も重要なのは、「複数人による共同意思決定」という特性です。個人顧客と異なり、家族では購買決定に複数のステークホルダーが関与します。父親、母親、子ども、時には祖父母までもが影響力を持ち、それぞれが異なる優先順位や判断基準を持っています。
日本の家族構造において特徴的なのは、依然として主要な購買意思決定者が母親であるケースが多い点です。博報堂生活総合研究所の調査によれば、日本の家計における日常的な購買決定の約70%は母親が担っているとされています。しかし、高額商品や家族全体に関わる重要な決定(住宅、車、家族旅行など)では、家族会議を通じた共同意思決定プロセスが取られることが一般的です。
ファミリー層向けカスタマージャーニーマップの作成ステップ

1. 家族内の役割と影響力の特定
ファミリー層向けのカスタマージャーニーマップを作成する最初のステップは、家族内の各メンバーの役割と影響力を明確化することです。
具体的には以下のような役割分担が存在します:
– 発案者(Initiator):最初に商品やサービスの購入を提案する人
– 影響者(Influencer):購入決定に対して意見や情報を提供する人
– 決定者(Decider):最終的な購入決定を下す人
– 購入者(Buyer):実際に購入行為を行う人
– 利用者(User):商品やサービスを実際に使用する人
例えば、家族旅行の場合、子どもが「ディズニーランドに行きたい」と発案し(発案者)、母親が複数の選択肢を調査して提案し(影響者)、両親が予算と相談して決定し(決定者)、父親がクレジットカードで支払い(購入者)、家族全員が体験を楽しむ(利用者)というパターンがあります。
2. 各接点における家族メンバーの関与度をマッピング
カスタマージャーニーの各段階(認知、検討、購入、使用、推奨)において、家族の誰がどのように関与するかを可視化します。これには、以下のようなマトリックスを作成すると効果的です:
| ジャーニー段階 | 父親の関与 | 母親の関与 | 子どもの関与 | 主な接点 |
|---|---|---|---|---|
| 認知 | 中 | 高 | 高 | SNS、テレビCM、友人の口コミ |
| 検討 | 高 | 高 | 中 | 口コミサイト、価格比較サイト、店舗訪問 |
| 購入 | 高 | 中 | 低 | ECサイト、実店舗 |
日本のファミリー層特有のジャーニーパターン
日本のファミリー層に特有のカスタマージャーニーパターンとして、以下の点に注意が必要です:
1. 情報収集の多様化と役割分担
日本の家族では、情報収集において世代間の役割分担が明確です。デジタルネイティブの子どもがSNSやYouTubeから情報を得て親に伝える「リバースメンタリング」現象や、母親が主にママ友ネットワークやLINEグループから情報を得るパターンが顕著です。博報堂DYメディアパートナーズの調査によれば、日本の母親の約65%が購買判断においてSNSやママ友からの情報を重視しているというデータがあります。
2. 安全性と信頼性の重視
日本のファミリー層は、特に子どもに関連する製品やサービスにおいて安全性と信頼性を最重視します。第三者機関の認証や長期間の実績がある企業の製品を選ぶ傾向が強く、新規ブランドへの抵抗感が比較的高いのが特徴です。
3. 実例:ファミリーカーの購入ジャーニー
例えば、ファミリーカーの購入プロセスでは、以下のようなカスタマージャーニーが一般的です:

– 認知段階:母親がSNSや友人から情報を収集し、子どもの成長に合わせた車の必要性を認識
– 検討段階:父親がカタログやWeb、専門誌で調査し、母親が安全性や使い勝手を重視した情報を収集、家族で複数のディーラーを訪問
– 決定段階:両親による予算と機能の最終判断、子どもの意見も考慮(特に色や内装など)
– 購入段階:主に父親が契約手続きを担当
– 使用・推奨段階:家族全員の満足度が高ければ、母親を中心に友人やSNSでの推奨行動
このようなファミリー層特有のカスタマージャーニーを理解し、各段階で適切なコミュニケーション戦略を構築することが、効果的なマーケティング活動の鍵となります。
タッチポイント最適化:ファミリー層の購買体験を向上させる効果的な接点設計
ファミリー層のタッチポイント設計の重要性
ファミリー層とのタッチポイント(接点)は単なる接触機会ではなく、ブランドストーリーを紡ぎ、顧客体験を形成する貴重な瞬間です。特に子どもを持つ家族は、個人の意思決定とは異なり、複数の家族メンバーの意見や都合を考慮する複雑な購買行動を示します。日本のファミリー層は特に、子どもの教育や家族の健康、時間の効率化などを重視する傾向があり、これらの価値観を反映したタッチポイント設計が成功の鍵となります。
調査によれば、日本のファミリー層の約78%が購入前に少なくとも3〜5つのタッチポイントと接触するというデータがあります。これは単身者や夫婦のみの世帯と比較して1.5倍以上の接点数です。この多様なタッチポイントを効果的に設計し、一貫したメッセージを届けることが重要です。
ファミリー層向けタッチポイントの種類と最適化アプローチ
1. デジタルタッチポイント
ファミリー層は時間的制約が大きいため、スマートフォンやタブレットを活用した情報収集が一般的です。特に日本では、親世代の約92%がスマートフォンを所有しており、子育て情報の収集や商品比較にデジタルチャネルを活用しています。
最適化ポイント:
・モバイルファーストの設計(スマホでの閲覧体験を最優先)
・子どもの年齢別コンテンツ分類(年齢に応じた商品提案)
・時短を意識した簡潔な情報設計(3分以内で必要情報が得られる構成)
・家族全員の意見を取り入れやすい共有機能(家族LINEグループへの共有ボタンなど)
実店舗タッチポイントの革新
オンラインの普及にもかかわらず、ファミリー層にとって実店舗体験は依然として重要です。特に子ども関連商品は、実際に見て触れる体験が購買決定に大きく影響します。イオンモールなどの大型商業施設が子ども向け体験スペースを拡充しているのはこのためです。
効果的な実店舗タッチポイント設計:
・子ども連れに配慮した店舗レイアウト(ベビーカー通路の確保、キッズスペースの設置)
・家族での試用体験が可能な商品展示(全員が参加できるデモンストレーション)
・ファミリー向け特典プログラム(家族会員制度、子ども同伴割引など)
・季節イベントと連動した体験型マーケティング(夏休み工作教室、クリスマスワークショップなど)
日本の玩具メーカーであるバンダイは、商品の「触れる」体験を重視し、全国の百貨店やショッピングモールに体験型ブースを展開。これにより親子の購買意欲を30%向上させることに成功しました。
カスタマージャーニーの各段階におけるタッチポイント最適化
ファミリー層のカスタマージャーニーは複数の意思決定者が関わる複雑なプロセスです。各段階に応じたタッチポイント設計が必要です。
認知段階: 家族の課題解決を前面に出したコンテンツマーケティング(育児の悩み解決、家族時間の充実など)が効果的です。子育てインフルエンサーとのコラボレーションも認知拡大に有効で、日本では「ママインフルエンサー」を活用したキャンペーンが平均28%の認知度向上に貢献しています。
検討段階: 家族メンバー全員の意見を取り入れやすい比較コンテンツや、レビュー機能が重要です。特に「他の家族の声」は強い説得力を持ちます。ファミリー層向けの商品比較サイトでは、「子どもの反応」「家族での使いやすさ」などの評価軸を設けることで、従来の比較サイトと差別化できます。
購入段階: 決済プロセスの簡素化と安全性の担保が鍵となります。また、家族特典(子ども用プレゼント、家族割引など)も購入を後押しします。イケアやコストコなど、ファミリー層に人気のブランドは、子ども連れでも快適な買い物体験と、家族向け特典を組み合わせることで高いロイヤルティを獲得しています。

利用・維持段階: 子どもの成長に合わせたフォローアップコミュニケーションが効果的です。例えば、購入した絵本や知育玩具の次のステップを提案するなど、子どもの発達段階に寄り添った継続的なコミュニケーションが家族との長期的な関係構築につながります。
タッチポイント設計の最終目標は、ファミリー層の「家族の幸せ」という根本的な価値観に寄り添い、真に役立つブランド体験を提供することです。一貫性のあるメッセージと、家族全員に配慮した接点設計が、ファミリー層の心を掴むマーケティングの要諦と言えるでしょう。
デジタルとリアルを融合したファミリー層向けオムニチャネル戦略
デジタルとリアルの境界を超えるオムニチャネル体験
現代のファミリー層は、オンラインとオフラインを行き来しながら購買行動を行っています。スマートフォンで情報収集しながら実店舗で商品を確認し、自宅に戻ってからオンラインで注文するといった複雑な購買パターンが一般的になっています。このような消費者行動に対応するためには、シームレスなオムニチャネル戦略が不可欠です。
オムニチャネル(Omni-channel)とは、すべての販売チャネルや顧客接点を統合し、一貫した顧客体験を提供する戦略を指します。特にファミリー層においては、以下の要素が重要になります。
日本のファミリー層に効果的なオムニチャネル施策
1. モバイルファーストの情報設計
日本の親世代の98.3%がスマートフォンを所有しているという総務省の調査結果があります。子育て中の親は片手で操作できるスマートフォンを活用して情報収集する傾向が強いため、モバイル体験の最適化は必須条件です。
具体的には:
– レスポンシブデザインの採用
– ページ読み込み速度の最適化(3秒以内を目標に)
– 片手操作を考慮したUIデザイン
– 音声検索への対応(「子ども連れで行ける〇〇」などの検索に対応)
実店舗とデジタルの融合事例
イオンモールの「スマートイオン」構想は、日本のファミリー層向けオムニチャネル戦略の好例です。店舗アプリを通じて、来店前の駐車場予約、店内ナビゲーション、レジ待ち時間の可視化などを実現し、子連れでの買い物ストレスを大幅に軽減しています。2022年の調査では、アプリ導入後の顧客満足度が23%向上し、滞在時間も平均15分増加したという結果が出ています。
また、トイザらスのAR(拡張現実)を活用した店舗体験も注目に値します。スマートフォンアプリを通じて商品の使用イメージをバーチャルに体験でき、子どもと親が一緒に商品選びを楽しめる工夫が施されています。
データ統合によるパーソナライズ戦略
オムニチャネル戦略の核心は、あらゆる顧客接点から得られるデータを統合し、一貫したパーソナライズを実現することにあります。ファミリー層においては、子どもの成長段階に合わせたタイムリーな提案が特に効果的です。

例えば、ベビー用品メーカーのピジョンでは、顧客データベースと連動したLINE公式アカウントを活用し、子どもの月齢に合わせた商品情報や育児アドバイスを提供しています。オンラインでの行動履歴と実店舗での購買データを組み合わせることで、より精度の高いレコメンデーションを実現しています。
ファミリー層向けオムニチャネル戦略の実装ステップ
1. 顧客データの統合基盤構築:オンライン・オフラインの顧客データを統合するCDP(Customer Data Platform)の導入
2. タッチポイント間の一貫性確保:ブランドメッセージや顧客体験の統一
3. 家族全体を視野に入れた設計:親と子それぞれの視点を考慮したジャーニー設計
4. デジタルとリアルの相互送客:オンラインからオフラインへ、またその逆の流れを促進する仕組み作り
5. 効果測定と継続的改善:オムニチャネル特有のKPI設定と定期的な検証
今後の展望と実践のポイント
ファミリー層向けのカスタマージャーニー戦略は、テクノロジーの進化とともに常に変化しています。特に注目すべきは、音声AIやIoTを活用した新たな顧客接点の創出です。例えば、スマートスピーカーを通じた家族全体とのエンゲージメント構築や、IoT家電との連携によるライフスタイル提案などが今後さらに重要になるでしょう。
最後に、どれだけテクノロジーが進化しても、ファミリー層マーケティングの本質は「家族の時間をより豊かにする」という価値提供にあります。テクノロジーはあくまでもその手段であり、目的ではないことを忘れないでください。データとテクノロジーを活用しながらも、常に家族の幸せという視点からカスタマージャーニーを設計することが、真に効果的なマーケティング戦略の鍵となるのです。
ピックアップ記事





コメント